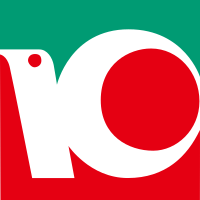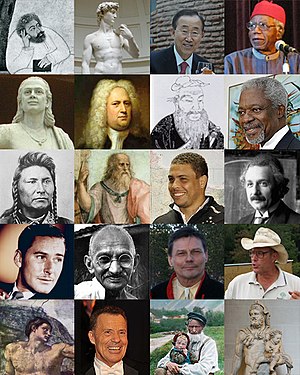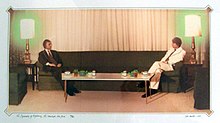-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
「730」に関する資料情報
PR
-
「愛染」に関する資料情報
愛染の概要 目次へ 
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2016年8月)
出典は脚注などを用いて記述と関連付けてください。(2016年8月)
独自研究が含まれているおそれがあります。(2016年8月)
言葉を濁した曖昧な記述になっています。(2016年8月)
愛染明王(『図像抄』〈十巻抄〉より) 木造愛染明王坐像 東京国立博物館蔵、鎌倉時代、重要文化財 愛染明王(仏像図彙 1783年)愛染明王(あいぜんみょうおう、梵: rāgarāja[1])は、仏教の信仰対象であり、密教特有の憤怒相を主とする尊格である明王の一つ。 -
「日刊スポーツ」に関する資料情報
日刊スポーツの概要 目次へ 
日刊スポーツ(にっかんスポーツ、NIKKAN SPORTS、略称:ニッカン)は、日本国内で発行される日刊のスポーツ新聞。朝日新聞系。
全国各地の4社から発行されている。
日刊スポーツ新聞社(にっかんスポーツしんぶんしゃ、東京都)
日刊スポーツ新聞西日本(にっかんスポーツしんぶんにしにっぽん、大阪府、愛知県、福岡県)
北海道日刊スポーツ新聞社(ほっかいどうにっかんスポーツしんぶんしゃ、北海道)
沖縄タイムス社(おきなわタイムスしゃ、沖縄県、印刷・発行委託)種類 日刊紙 サイズ ブランケット判 事業者 株式会社日刊スポーツ新聞社株式会社日刊スポーツ新聞西日本株式会社北海道日刊スポーツ新聞社株式会社沖縄タイムス社 本社 東京都中央区築地3-5-10大阪府大阪市北区中之島2-3-18(西日本・大阪本社)愛知県名古屋市中区栄1-3-3 朝日会館13階(西日本・名古屋本社)福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル7階(西日本・西部本社)北海道札幌市中央区北3条東3丁目1-30沖縄県那覇市久茂地2-2-2 - 「成田空港」に関する資料情報
-
「ロケット」に関する資料情報
ロケットの概要 目次へ 
ロケット(英: rocket)は、自らの質量の一部を後方に射出し、その反作用で進む力(推力)を得る装置(ロケットエンジン)、もしくはその推力を利用して移動する装置である。外気から酸化剤を取り込む物(ジェットエンジン)は除く。
狭義にはロケットエンジン自体をいうが、先端部に人工衛星や宇宙探査機などのペイロードを搭載して宇宙空間の特定の軌道に投入させる手段として使われる、ロケットエンジンを推進力とするローンチ・ヴィークル全体をロケットということも多い。
また、ロケットの先端部に核弾頭や爆発物などの軍事用のペイロードを搭載して標的や目的地に着弾させる場合にはミサイルとして区別され、弾道飛行をして目的地に着弾させるものを特に弾道ミサイルとして区別している。なお、北朝鮮による人工衛星の打ち上げは国際社会から事実上の弾道ミサイル発射実験と見なされており国際連合安全保障理事会決議1718と1874と2087でも禁止されているため、特に日本国内においては人工衛星打ち上げであってもロケットではなくミサイルと報道されている。
なお、推力を得るために射出される質量(推進剤、プロペラント)が何か、それらを動かすエネルギーは何から得るかにより、ロケットは様々な方式に分類されるが、ここでは最も一般的に使われている化学ロケット(化学燃料ロケット)を中心に述べる。
ロケットの語源は、1379年にイタリアの芸術家兼技術者であるムラトーリ[1]が西欧で初めて火薬推進式のロケットを作り、それを形状にちなんで『ロッケッタ[2]』と名づけたことによる。 - 「拍手」に関する資料情報
- 「オークワ」に関する資料情報
- 「マナマ」に関する資料情報
- 「宇宙空間」に関する資料情報
-
「オランダ」に関する資料情報
オランダの概要 目次へ 
オランダ(オランダ語: Nederland [ˈneːdə(r)lɑnt]、[ˈneɪ̯də(r)lɑnt] ( 音声ファイル); 西フリジア語: Nederlân; パピアメント語: Hulanda)は、西ヨーロッパに位置する立憲君主制国家。東はドイツ、南はベルギーと国境を接し、北と西は北海に面する。ベルギー、ルクセンブルクと合わせてベネルクスと呼ばれる。憲法上の首都はアムステルダム(事実上の首都はデン・ハーグ)。
カリブ海のアルバ、キュラソー、シント・マールテンと共にオランダ王国を構成している。他、カリブ海に海外特別自治領としてボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島(BES諸島)がある。公用語 オランダ語[注 1] 首都 アムステルダム[注 2] 最大の都市 アムステルダム 国王 ウィレム=アレクサンダー - 「か月」に関する資料情報
-
「岩石」に関する資料情報
岩石の概要 目次へ 
岩石(がんせき、英: rock[1])とは、世間一般には、岩や石のこと[2]。石の巨大なもの、特に無加工で表面がごつごつしたものを岩(いわ)と呼び、巌[注 1]、磐とも書く[4]。
学術的には、自然的原因による起源をもつ[5]、数種あるいは一種類の鉱物や準鉱物(火山ガラスなど)の集合体を指す[6][7][8]。たとえば、花崗岩は、石英、長石、雲母、角閃石など、さまざまな鉱物の集まりから成る[9]。露頭での見かけ(産状)上は、層状である岩石(成層岩・層状岩)を地層と呼ぶのに対し、貫入している(貫入岩)か塊状のもの(塊状岩)を岩石として区別する[10]。岩石は地球表層の地殻と上部マントルの一部をはじめ、他の地球型惑星や小惑星、衛星を構成する主要な物質である[7][11]。
地殻の岩石は成因的に、マグマ(岩漿)が冷え固まること(火成作用(英語版))でできる火成岩[12][13]、岩石の砕屑物、生物の遺骸、化学的沈殿物などが堆積または沈積(堆積作用)し、固結(続成作用)してできる堆積岩[13][14]、既存の岩石が高い温度と圧力を受けて固体のまま組成や構造が変化(変成作用)してできる変成岩[13][15]の3つに大きく分類することができる[6][16][17]。さらに、共に地球の内部でできた岩石である火成岩と変成岩をまとめて内成岩、地表(地球の外部)でできた岩石である堆積岩を外成岩として大別する方法もある[17]。 -
「起動」に関する資料情報
起動の概要 目次へ 
ブート(英: boot)またはブートストラップ(英: bootstrap)は、コンピュータシステムの電源投入時、あるいはシステムのリセット後、モニタやOSなどなんらかの基本的なシステムソフトウェアを主記憶に展開し、ユーザプログラムを実行できるようにするまでの処理の流れをいう。ブートローダ(英: boot loader)は、以上のプロセスで使われるローダ、すなわち不揮発性の補助記憶にある目的のプログラムを読み出し、揮発性の主記憶に書き込むプログラムのことである。
電源投入時のブートのことを「コールドブート」、リセットされたことによるブートを「ウォームブート」という。ウォームブートでは、コールドブートにおける最初のほうの手続きのいくつかが必要無い場合もあり、そういった手続きを省略することもある。
ブートストラップまたはブートストラップローダ(英: bootstrap loader)という名前は、ブーツのつまみ革(英: strap)を自分で引っ張って自分を持ち上げようとするイメージから来ている[1]。つまり、コンピュータはプログラムをロードしないと動作できないが、プログラムをロードするプログラムはどうロードするのだ? というパラドックスに着目した呼称である[2]。 -
「アルミ」に関する資料情報
アルミの概要 目次へ 
アルミニウム(羅: aluminium[2]、英: aluminium, aluminum [ˌæljəˈminiəm, əˈljuːmənəm])は、原子番号 13、原子量 26.98 の元素である。元素記号は Al。日本語では、かつては軽銀(けいぎん、銀に似た外見をもち軽いことから)や礬素(ばんそ、ミョウバン(明礬)から)とも呼ばれた[3]。アルミニウムをアルミと略すことも多い。
「アルミ箔」、「アルミサッシ」、一円硬貨などアルミニウムを使用した日用品は数多く、非常に生活に身近な金属である。天然には化合物のかたちで広く分布し、ケイ素や酸素とともに地殻を形成する主な元素の一つである。自然アルミニウム (Aluminium, Native Aluminium) というかたちで単体での産出も知られているが、稀である。単体での産出が稀少であったため、自然界に広く分布する元素であるにもかかわらず発見が19世紀初頭と非常に遅く、精錬に大量の電力を必要とするため工業原料として広く使用されるようになるのは20世紀に入ってからと、金属としての使用の歴史はほかの重要金属に比べて非常に浅い。
単体は銀白色の金属で、常温常圧で良い熱伝導性・電気伝導性を持ち、加工性が良く、実用金属としては軽量であるため、広く用いられている。熱力学的に酸化されやすい金属ではあるが、空気中では表面にできた酸化皮膜により内部が保護されるため高い耐食性を持つ[4]。名称, 記号, 番号 アルミニウム, Al, 13 分類 貧金属 族, 周期, ブロック 13, 3, p 原子量 26.9815386(13) -
「ISS」に関する資料情報
ISSの概要 目次へ 
国際宇宙ステーション(こくさいうちゅうステーション、英: International Space Station、略称:ISS、仏: Station spatiale internationale、略称:SSI、露: Междунаро́дная косми́ческая ста́нция、略称:МКС)は、アメリカ合衆国、ロシア、日本、カナダ及び欧州宇宙機関 (ESA) が協力して運用している宇宙ステーションである。地球及び宇宙の観測、宇宙環境を利用した様々な研究や実験を行うための巨大な有人施設である。地上から約400km上空の熱圏を秒速約7.7km(時速約27,700km)で地球の赤道に対して51.6度の角度で[9]飛行し、地球を約90分で1周、1日で約16周する。なお、施設内の時刻は、協定世界時に合わせている。
1999年から軌道上での組立が開始され、2011年7月に完成した[10]。当初の運用期間は2016年までの予定であったが、アメリカ、ロシア、カナダ、日本は少なくとも2024年までは運用を継続する方針を発表もしくは決定している[11][12]。運用終了までに要する費用は1540億USドルと見積もられている(詳細は費用を参照)。COSPAR ID 1998-067A コールサイン Alpha 乗員数 6人 打上げ日時 1998年–2011年 - 「北青山」に関する資料情報
- 「320」に関する資料情報
- 「観覧席」に関する資料情報
- 「男性」に関する資料情報
- 「最悪」に関する資料情報
- 「木造住宅」に関する資料情報
- 「悪質」に関する資料情報
- 「外交」に関する資料情報
- 「事務所」に関する資料情報
- 「下呂市」に関する資料情報
カテゴリー
最新記事
(09/07)
(12/16)
(10/14)
(09/06)
(08/21)