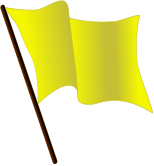-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
「習近平」に関する資料情報
習近平の概要 目次へ 
習 近平(しゅう きんぺい、簡体字: 习近平、拼音: Xí Jìnpíng、漢族、1953年6月15日 - )は、中華人民共和国の政治家。中国共産党の第4世代の最高指導者であった胡錦濤の後任として、2012年より第5代[注 2]中国共産党中央委員会総書記、第6代中国共産党中央軍事委員会主席、2013年より第7代中華人民共和国主席、第4代中華人民共和国中央軍事委員会主席を務め、中華人民共和国の最高指導者の地位にある。太子党のひとりで、父は習仲勲(元国務院副総理)。 任期 2012年11月15日 – 指導部 第18期政治局常務委員会1. 習近平2. 李克強3. 張徳江4. 兪正声5. 劉雲山6. 王岐山7. 張高麗 任期 2013年3月14日 – 副主席 李源潮 PR - 「宇都宮線」に関する資料情報
- 「セブン銀行」に関する資料情報
- 「両国国技館」に関する資料情報
-
「ホンダ・カブ」に関する資料情報
ホンダ・カブの概要 目次へ 
1958年(昭和33年)のC100に始まるシリーズで、世界最多量産のオートバイならびに輸送用機器である。
高性能・高耐久性により、それ以前の日本市場に存在していた同クラス小型オートバイのみならず、簡易な補助エンジン自転車と上位クラスのスクーター[注 5]との双方を一挙に圧倒する大成功を収めた。搭載される空冷4ストロークエンジンの動弁機構をOHVからSOHCへ、燃料供給をキャブレターからインジェクションへの変更など機構改良は多岐にわたるが、2010年代に至るまで基本設計の多くが継承され、日本国内および国外で生産される。2011年(平成23年)には同社が小型二輪車の生産拠点海外移管を計画したことから、2012年(平成24年)のモデルチェンジで日本国内での生産終了を発表したもののアベノミクス効果による円安を受けて方針転換。2017年(平成29年)には、再び全モデルが同社熊本製作所での継続生産となった。
開発・製造の経緯[編集]1950年代中期に至ると初期の経営を支えた自転車後付け式のエンジンキットも同クラスの類似競合製品が増加し、前述したカブF型も安穏としていられる状況ではなくなりつつあった。
また戦後復興が進んだ日本のオートバイ市場でも簡易な自転車補助エンジンに不満を持つユーザーからは、富士重工業(現・SUBARU)製「ラビット」・中日本重工業(現・三菱重工業)製「シルバーピジョン」に代表される125cc - 250ccクラスの上級スクーターが、運転しやすさや性能面のゆとりにより支持されるようになっていた。
このような市場趨勢をマネジメントの見地から考慮した藤沢武夫は、カブF型の後継モデルとなり得る廉価な実用的小排気量オートバイの開発・製造販売を考えた。藤沢は「(商品として)カブのような自転車に取り付ける商品ではなく、50ccエンジンとボディぐるみのもの(完成車)が欲しい」と本田宗一郎に訴えたが、本田は技術を担う立場からの判断で当初は「(50cc完成車として)乗れる(性能の)ものは作れない」と一蹴していた[注 6]。
しかし藤沢は、1956年の欧州視察旅行往路旅客機中で50cc級完成車の件を再び本田に持ちかけた。本田も最初はうるさがっていたが、藤沢の熱心さにようやく関心を持ち始め、結果として道中でクライドラーやランブレッタなどの欧州製スクーター・モペッドなどを見かけると「これはどうだ」と藤沢に尋ねるようになった。問答を重ねるうち、本田は藤沢の求める商品性の高い新製品のイメージを膨らませるようになった。そのコンセプトからは、もはや従来のカブや欧州製モペッドのような自転車式ペダル[注 7]は排除されていた。
帰国後には本田の陣頭指揮により、新型モペッドの開発が開始された。特に耐久性の高い高回転4ストロークエンジンと変速を容易化するクラッチシステムの実用化には苦心を重ね、最終的に、50ccクラスながら既存上位排気量車にも比肩する出力を絞り出す高回転エンジンと、無段変速機付スクーターにこそ及ばないものの変速操作を容易にした自動遠心クラッチ式変速機とを揃って完成させた。
1957年末に本田から研究所へ呼び出された藤沢は、自転車取付式エンジンのような足漕ぎペダルを排除したスマートなモペッドの実物大模型とスペックを示された。藤沢はその場で「これなら3万台は売れる」と述べた。本田や開発陣は「年間でか?」と見積もりのスケールに感嘆したが、藤沢は「月間だ」と真意を補足し、一同をさらに驚嘆させた。当時の同社主力商品であるドリームとベンリィを合算した生産台数は、月産で6,000から7,000台。さらに日本全国の二輪車販売台数が2万台程度であったから、藤沢の見積もりが正しければ、競合メーカー同級車種を圧倒するばかりかオートバイ市場そのものが一挙に押し広げられることも意味した。
CA100スーパーカブC100輸出仕様トヨタ博物館所蔵車C100スーパーカブは1958年6月から生産開始、8月に発売された。若干の初期不良は見られたものの比較的短期間で生産・販売は軌道に乗り、生産台数は1958年度約2万4,000台、1959年度16万7,443台、1960年度56万4,365台を達成。月産30,000台体制を見込み多額の投資で新たに鈴鹿製作所を建設したが、当初の「過剰設備ではないか」との危惧も数年のうちに杞憂に終わりフル稼働することになった。
日本の小型オートバイ・スクーター市場は、1950年代の一時は大小数十のメーカーが群雄割拠の状態にあったが、スーパーカブの発売から数年で、中堅・零細のアッセンブリー・メーカーは市場から一掃された。生き残った大手・中堅メーカーも相次いで本モデルの類似モペッドを開発して追随し、可能性を高く評価した藤沢の予見は事実となった。
発売当時の画期的な試みとして、レッグシールドやカバー[注 8]などの直接応力のかからないパーツに大型プラスチック素材(ポリエステル)が使われ、軽量化や組み立て合理化に役立った[注 9]。
簡潔で軽量かつ堅牢な全体構造に、強力なエンジンと扱いやすい変速機を組み合わせた結果、生産から60年近く経つ最初期モデルであっても、充分に整備されていれば21世紀初頭の都市交通の流れに乗れ、また業務用に使用しても何ら支障の無いほど高水準の性能を得ている。その当初から、極めて完成度の高い工業製品となった。
車体[編集]太いパイプとプレス鋼板で構築されたフレームに、耐久性に富みしかも低燃費な排気量49ccの自然空冷式4ストローク単気筒エンジン[注 10]を水平に近い前傾80°シリンダーとして搭載。自動遠心式クラッチを組み合わせた常時噛合式3段変速機とフルカバードされたチェーンで後輪を駆動する。一部車種には4段変速機搭載車もあるが、いずれも変速方式はロータリー式[注 11]を採用する。なお自動遠心クラッチにより、ハンドレバーによる操作は不要のため日本の運転免許制度では、小型自動二輪車・普通自動二輪車・大型自動二輪車のオートマチック限定免許でも運転が可能である[注 12]。
フラットなステップフロアを持つスクーターほどではないが、婦人用自転車に近いほどに運転者前方のフレームを低く通してあるため、スカートを履いた女性でも容易に両足を渡して乗車できるようになっている。この構造だと、サドル前方のフレームに燃料タンクを取り付ける一般的オートバイのレイアウトは使えないが、低く下がったフレームの上に燃料タンクを配置し、これをそのままサドルを載せる土台にも利用する極めて合理的な配置で解決した[注 13]。
ウインカースイッチは一般的なオートバイと異なり、スロットルグリップがある右手側に、上下動作式のスイッチが装備された。
車体には、射出成形プラスチック製の大型レッグシールドが装備され、風防効果を得ている。さらにこのレッグシールドは、単独のシュラウド(冷却用外覆)や強制空冷ファンを持たない自然空冷エンジンを、両側から抱え込む配置であり、ヘッドが前方に傾斜してシリンダー部が走行風に相対しないエンジンに、冷却空気を誘導する役割も担う。なおかつレッグシールドのエンジン真上、運転者の足下両サイドには穴が開き、誘導された冷却風の熱気抜けを良くする配慮もなされている。
車輪は、前後とも17インチ径を採用した。それまでのオートバイは主に18インチもしくは16インチを採用しており、イレギュラーな規格ということで、開発当時はタイヤ製造メーカーから、製造を断られたこともあったが、性能から割り出されたこの車輪径は、一時ビジネスバイクのデファクトスタンダードにまでなった。ただし現在は、ライバル他車だけでなく、カブ一部車種で14インチも採用する。
全体に軽量化されているため、古い商店の玄関などで、外と土間の間に少々高い敷居があっても、自転車同様に、人手で乗り越えさせ、屋内に乗り込ませることが容易である。
また数度のモデルチェンジで、設計時の基本フォルムは保ちながらもデザインの微修正は実施されており、これによって、モデルイヤーを判別する基準にもなっている[注 14]。
動力系[編集]自動遠心クラッチとロータリー式変速機構を備えた構成は、本田宗一郎が示した「蕎麦屋の出前持ちが片手で運転できるようにせよ[注 15]」という条件に応え左手のクラッチレバーを廃した結果である。つま先の掻き上げ操作に適さない雪駄などの履物でも変速操作を可能とするため、シフトペダルにはかかと用の踏み返しが付けられた。この形式のシフトペダルは競合各社も追随採用し、その形状から日本市場で「シーソーペダル」と呼ばれるようになる。1960年(昭和35年)12月までの日本では50cc以下の原動機付自転車に運転免許が必要なかったことや、法規による交通規制が緩く、片手運転や雪駄履き運転も想定せざるを得なかった当時のおおらかさを物語るエピソードだが、独特の変速機構は結果として乗り易さに大きく寄与した。
エンジン[編集]シンプルな自然空冷式の4ストローク単気筒エンジンで実用優先なチューニングだが、8,000rpm以上の高回転を許容する設計から高耐久性ならびに経済性に優れ、定期的なオイル交換のみで長期使用に耐える。
50ccモデルの1958年製造開始時最高出力は4.3ps(≒3.16kW)で、当時における2ストローク同級排気量の競合車各車に比してほぼ2倍、既存の90-100ccモデルにすら比肩する突出した性能を誇った。その後の改良で1980年代前半には最高出力は5.5ps(≒4.05kW)まで向上したが、1980年代半ば以降は自主規制や環境対策から最高出力を落とし、開発の方向を馬力向上から実燃費向上へと転換した。厳しい排ガス規制の影響を受けて2007年9月のAA02E型では過去最低の3.4ps(≒2.5kW)まで落ち込むが、技術改良を進めることで2012年5月のAA04E型では3.7ps(≒2.7kW)と僅かなら上昇した。
前傾80°シリンダーを持つことから横型エンジンとも呼ばれ、バルブレイアウトと燃料供給機構以外に基本設計は当初から大きく変更されていない。内径x行程を変化させることによる排気量バリエーションを構成する。以下で現在までの大きな設計変更について解説する。
動弁機構当初はOHVであったが、1964年2月発売のC65(排気量63cc)でSOHCを初採用。以後は排気量ごとで順次SOHC化が実施され、主力の50ccモデルは1966年5月に変更。燃料供給装置2007年9月21日に平成18年度排気ガス規制へ適合させるマイナーチェンジでは、カスタムを含む50ccシリーズ全車でキャブレターからPGM-FI電子制御式燃料噴射装置へ変更を実施しシリーズ初採用となった。また同時にエキゾーストパイプ内に三元触媒を装着した。この結果エンジン型式がAA01EからAA02Eに変更されるとともにクランクケースの黒塗装化を実施した。内径x行程50ccモデルは、OHV時代が40.0x39.0(mm)、SOHC化後は39.0x41.4(mm)とされたが、2012年のAA04E型へのモデルチェンジで37.8x44.0(mm)へ変更。消音また排気量に対してマフラー容量を大きくし[注 16][注 17]、4ストロークエンジンと相まってオートバイとしてはエンジン騒音を特段に低下させた[注 18]。燃費非常に低燃費であることでも知られており、50ccモデル30km/h定地走行テストの過去最高値は1983年2月23日に発売された50スーパカスタムの180km/Lである。この数値は環境対策などから、キャブレター最終モデルのAA01E型では146km/L、それ以降のAA02E型では110 - 116km/Lに低下した。定地走行テスト値は燃費テスト用のベストな条件を整えた場合の非現実的な物で、実際の50ccモデル公道走行燃費は、法定30km/hを遵守した運転で60 - 90km/L、アクセル全開や高速での走行などラフな使い方で45 - 60km/L程である[注 21]。それでも内燃機関動力の陸上車両では特に燃費効率に優れる存在である。2013年より導入されたWMTCモード値では、50ccモデルが75.2km/L、110ccモデルが65.6km/Lとされる。
本田技研工業主催による低燃費競技会「Honda エコ マイレッジ チャレンジ」では、市販状態のスーパーカブ50がエントリーする市販車クラスで最高541.461km/L、カブのエンジンを元にした専用競技用車両では3,000km/Lを越える記録が樹立された。
耐久性[編集]開発当時の日本の道路は、国道であっても「酷道」と呼ばれる悪路が多く、過積載などの無茶な運転も横行しており、それらを考慮して設計製造が行われた。さらにはビジネスユースという点からも耐久性が重視されていることから、走行距離にして何十万キロ耐えられるのかは、本田技研工業でさえも「想像が付かない」との見解を下している。
「エンジンオイルの代わりに天ぷら油や灯油を詰めても走行する。新車から廃車までオイル交換がなされていない個体もある。」と伝えたテレビドキュメンタリー番組が存在する。開発陣の見解は「公式に実験や確認を行った訳ではないながらも恐らく事実である」としている[注 22]。これは各部が受ける熱や圧力が小さく、エンジンオイルへの負担が相対的に少ないという点に起因するものである。また冷間発進が多い出前に使われる車両よりも連続走行時間の長い郵便配達で使われる車両の方が寿命が長いという報告もある。
過去にディスカバリーチャンネルで耐久性を検証するテレビ番組が放映されたが、エンジンオイルの代わりにハンバーガーショップの使用済みフライヤー油脂[注 23]を使用し、山ほどのスイカやピザを積載し街中を走ってもトラブルを起こさず、あげく高層建築物の屋上から投げ捨てられた後もエンジンがかかりホイールは曲がったもののギアは入り(僅かだが)前進するなど、改めてタフネスぶりを証明した結果となった。
また本エンジンは、モンキー・ゴリラと共通する部品が多いこと、ベトナムやタイ王国ではカブが広く普及していること、海外生産パーツも豊富[注 24]なことから、部品を板金屋が自作する『各種チューニング』も多数実施されている。
日本でのユーザー層[編集]出前機装着車スーパーカブ90(交番用警察仕様)業務用途では、中華料理店や蕎麦店など飲食店の出前・商店の小口配達や配送・電力会社や銀行などの集金営業・近距離の巡回輸送・新聞販売店による一般家庭への配達など広範に用いられる。17インチ大径タイヤと耐久性を重視した構造が悪路にも耐えることから、農村を中心とした地方の高齢者にも愛用者は多く鍬や鎌を荷台にくくりつけて農作業の足代わりと使用されるケースも確認できる。
上述した出前用途では自転車用として開発された出前機が多数転用され大量に普及した副次効果も確認できるほか、郵便・新聞の配達業務では特化したバリエーションとしてMDシリーズやプレスカブも開発された。
納入先の要求による仕様変更にも対応しており、交番配備のパトロールバイクとして導入している警察仕様では、取り外して簡易盾としても使用できる透明ハンドル付きのウインドシールド・警棒収納ケース・書類を入れるスチール製ボックスなどを装備する。さらにかつては食糧庁(現・農林水産省食料産業局・生産局穀物課)納入の小豆色、電電公社(現・NTTグループ)納入の若竹色など専用塗装車が製造された。
個人用途では、市街地移動から耐久性と低燃費から長距離ツーリングやアドベンチャーランまで様々であるが、趣味的観点からドレスアップパーツやチューニングパーツで改造を楽しむ層もおり、海外製パーツも特にカブが普及しているタイ製などが輸入可能で日本国内に専門店もある。さらに近年の傾向として、市街地での駐車違反取締強化や石油価格高騰の影響により、スクーターを含めた原付一種・二種(小型自動二輪車)の所有使用者が増加する傾向があり、カブでも同様な現象が確認される。
また珍しい例としては鹿児島県立種子島中央高等学校が通学用バイクに指定している。
過去の販売車種[編集]スーパーカブC100スーパーカブ70輸出仕様スーパーカブ90カスタム輸出仕様排気量別に多数のモデルが製造された。本項では日本国内で販売されたモデルについて解説を行う。
スーパーカブC100
1958年8月発売の50ccOHVエンジン搭載モデル。スーパーカブC102
1960年4月発売。C100にセルフスターターモーターを装備したモデル。スーパーカブC105
1961年8月発売。上述したC100へ2人乗車可能とするためエンジン内径を42mmへ拡大し排気量を54ccへアップさせたモデル。スーパーカブCD105
1961年8月発売。上述したC105にセルフスターターモーターを装備したモデル。スーパーカブCM90
1964年10月発売。89ccSOHCエンジン搭載モデル。スーパーカブC65
1964年12月発売。C105からのモデルチェンジ車でSOHCエンジン搭載モデル。スーパーカブ50(型式:C50→AA01)
1966年5月に発売されたSOHCエンジン搭載モデル。1999年モデルから型式名をBA-AA01に変更。排出ガス規制に対応するため燃料供給装置をインジェクション化した2007年モデルから型式名をJBH-AA01に変更。2012年製造終了。スーパーカブ70(型式:C70)
1968年1月発売。スーパーカブ50用49ccエンジンをボアアップさせた72ccSOHCエンジンを搭載する。1998年12月に発売された1999年モデルを最後に製造終了。スーパーカブ90(型式:C90→HA02)
1968年12月発売。型式C90は89ccSOHCエンジンを搭載する。1980年3月のモデルチェンジで型式をHA02に変更。スーパーカブ50用49ccエンジンをボア・ストロークアップさせた85ccSOHCエンジンを搭載する。2008年製造終了。カブ100EX・スーパーカブ100
タイホンダマニュファクチュアリング社製輸入車。スーパーカブ90の85ccエンジンを97ccに排気量アップしたSOHCエンジンを搭載する。1988年・1989年モデルはカブ100EX(型式:HA05)。1993年・1995年モデルはスーパーカブ100(型式:HA06)。スーパーカブ110・スーパーカブ110PRO(型式:JA07)
スーパーカブ110スーパーカブ110 PROメーターパネル90ccシリーズが自動車排出ガス規制に伴い2008年9月に生産終了となったことから、原付二種(小型自動二輪車)クラス後継車種の販売再開が熱望された。しかし90ccが日本国内のみの生産だったことや日本国外で生産されているシリーズ車種が100 - 125cc中心だったことから、後継車種の開発はスケールメリットの点から日本国外生産車両と仕様共通化させることになり設計開発されたのが本モデルである。このためエンジンおよびパーツの6割は日本国外シリーズ車種の生産中心地となっているタイから輸入されており、全体的な車体の組み立ては熊本製作所で行われ、以下の2車種が製造販売された。スーパーカブ1102009年6月19日発売。型式名EBJ-JA07。車体番号JA07-100****・110****・120****。車体はタイホンダマニュファクチュアリング社のドリームをベースにしたことから、国内仕様としては初となるパイプおよびピボットプレートの組み合わせによるフレームとフロントサスペンションにテレスコピック式を採用。外装はプラスチック部品を多用しながらもカブのイメージを最大限に残したデザインとした。エンジンもドリーム同様のウェーブと部品を共通化させた109ccエンジンを採用。最高出力は日本国内の規制に適合させた上で90ccより1.2ps(≒0.88kW)向上させた 8.2ps(≒6.03kW)をマーク。トランスミッションも同様に2段クラッチ方式の4段変速機を搭載し、変速方式は停止時のみロータリーとなる変則リターン式が採用された。またカブシリーズでは初採用となるマルチリフレクターヘッドライト・左側プッシュキャンセルウインカー・メインスイッチ一体型ハンドルロックなどが装備された。車体色は当初コスタブルーとアバグリーンの2色を設定。2010年2月18日にコルチナホワイトを、同年8月20日にプコブルーとバージンベージュを追加し計5色とされた。スーパーカブ110 PRO2009年10月16日発売。型式名は同じで車体番号はJA07-300****。新聞配達や宅配用途に特化させた1人乗り専用設計とされ以下の変更が行われた。フロントキャリアに大型バスケットとリアキャリヤを搭載。
ヘッドライトとフロントウインカーをフロントバスケット前面に移設。
前後ホイールサイズを14インチ化。
専用強化サスペンションを装着。
車体色はコスタブルーのみの設定。
また郵政仕様となるスーパーカブ110MDのベース車両[注 25]でもあり、装備品は一部を除き共通化された。小型二輪車生産拠点海外移管計画により2012年で生産終了。
JA07型スーパーカブ諸元車名スーパーカブ110スーパーカブ110 PRO型式EBJ-JA07全長 x 全幅 x 全高 (㎜)1810 x 715 x 10451845 x 715 x 1040ホイールベース1190㎜1205㎜最低地上高140㎜105㎜最小回転半径1800㎜1900㎜シート高735㎜車両重量93㎏104㎏乗車定員2人1人50㎞/h定地走行燃費[注 26]63.5㎞/ℓ66.2㎞/ℓエンジン型式JA07E構造空冷4ストロークSOHC単気筒総排気量109㏄内径 x 行程50.0㎜ x 55.6㎜圧縮比9.0最高出力8.2ps(6.0kw)/7,500rpm最大トルク0.86㎏・m(8.4N・m)/5,500rpm点火方式フルトランジスタ式バッテリー点火燃料供給電子式燃料噴射(PGM-FI)始動方式セルフ・キック併用潤滑方式圧送飛沫併用式燃料タンク容量4.3ℓクラッチ自動遠心変速方式リターン(停止時のみロータリー)トランスミッション常時噛合4段1速2.6152速1.5553速1.1364速0.9161次減速比4.058最終減速比2.4282.142フレーム形式バックボーン前サスペンションテレスコピック後サスペンションスイングアームキャスター26°50′27°20′トレール77.0㎜64.0㎜タイヤ(前)2.25-17 33ℓ70/100-14 M/C 37Pタイヤ(後)2.50-17 43ℓ80/100-14 M/C 49Pブレーキ(前・後)機械式リーディングトレーリング標準本体価格238,000円276,000円グレード[編集]C50・C70・C90では、装備品などの違いにより以下のグレードが設定された。
スタンダード
ロータリー3段トランスミッションを搭載する最もオーソドックスなモデル。1980年モデルからは事故防止の観点から、走行中に3速からニュートラルにシフトチェンジを防止するドラムロックプレートがミッション内部に追加装備された。デラックス
スタンダードの豪華版でメタリック塗装を採用。スーパーデラックス
1982年にスタンダードの上級仕様として発売された仕様。丸みを帯びたスタンダードと異なり、全般的に角ばったデザイン・角型ヘッドライト・大型スピードメーターを採用。燃料計はスピードメーター内に装備する[注 27]。スーパーカブ70(72cc)・スーパーカブ90(85cc)はセルスターター・キックスターター併設。セルスターター機構以外は電圧に6V・12Vの相違点はあるが、基本的にデラックスと同スペックのエンジンを搭載する。スーパーカブ50はセル・キック併用仕様とキックのみの2仕様が設定された。なお同モデルは4段トランスミッションのほか、エンジンもスタンダードと異なる最高出力5.5ps/9000rpmの4サイクルエコノパワーエンジンを搭載した。スーパーカスタム
スーパーデラックスの名称を変更し1983年から販売された仕様[注 28]。50ccモデルはフロントサスペンションにアンチリフト機構を追加し、ギア比ならびに4サイクルエコノパワーエンジンの最高出力を5.0ps/8000rpmへ変更。カスタム
スーパーカスタムの名称を変更し1986年から販売された仕様。50ccモデルはキックスターター仕様を廃止。セル・キック併用仕様のみとなり、スタンダードと同スペックの最高出力4.5ps/7000rpmエンジン搭載へ変更。ビジネス
1985年 - 1998年に50ccモデルのみで販売された。ミッション内のドラムロックプレートを排し、走行中に前シフトチェンジで3速からニュートラルにシフト変更可能にしたビジネス仕様。トランスミッション変速比はスタンダードと共通だが、スプロケットを変更し2次減速比をカスタムと同じ数値に変更。ストリート
2001年にスタンダードの1バリエーションとして追加されたモデルであるが、好評のため2002年からストリートとして正式に独立。2007年まで製造販売された。スタンダードの車体にリトルカブ用のカラフルなカラーリングやリヤキャリアを装備する。新聞配達用特化モデル[編集]以下の2モデルが製造販売された。
プレスカブ50ニュースカブ901971年3月15日に生産累計600万台達成記念として受注生産。反響の大きさから翌1972年に正式モデルとなった。
雨天・早朝でも視認性の高いイエローの専用車体色。
防水性バッグ・大型キャリアを標準装備。
電装を12V化しセルスターターを搭載。
ブレーキライニング材質・サイドスタンドを強化。
リヤウインカー移設
プレスカブ501988年2月25日発売。スタンダードとグリップヒーターを装備するデラックスの2グレードが製造された。スーパーカブ50と共通のマイナーチェンジを実施したため型式はC50→AA01。2012年に製造中止。
大容量フロントバスケット・大型リヤキャリヤを標準装備。
積載量に応じてハンドルトップ⇔フロントバスケット前に切換可能なヘッドライト。
サイドスタンド・スイングアーム・リヤサスペンションを強化。
リヤブレーキ径を130mmに大型化。
完全に停止しなくても3速→ニュートラルへのチェンジが可能なロータリー式3段トランスミッションを搭載。
リトルカブ[編集]リトルカブ2007年モデル1997年8月8日発売。型式名A-C50。おしゃれに乗りたい若者・女性ならびに年配の扱いやすさを求めていたセグメントを意識しつつ、シャリィ販売中止に伴う代替も考慮し開発された。
エンジンは排気量50ccのみとし、キック始動のみの3段トランスミッションモデルとセル・キック併用4段トランスミッションモデルの2車種を設定。標準車との相違点を以下に示す。
ホイール径を17インチから14インチに変更しシート高を30mm下げた。このため全長もやや短縮するなど車体がよりコンパクトになった結果、小回りの効きと扱いやすさの向上が図られた。
カラフルなカラーリングをラインナップ。
フレームはスーパーカブ50と同じであるが、装着するパーツは随所に丸みを持った独自の装飾デザインを採用。ハンドル周り・フロントフォーク・前後ウインカー・チェンジペダル・ブレーキペダル・ステップバー・サイドカバー・レッグシールド・フロントフェンダー・マフラー等は専用部品である。シートやリヤキャリアも車体に合わせて一回り小型化されているが、これらはスーパーカブ50と互換性があり相互で交換が可能である。
発売後は以下のマイナーチェンジを実施した。
1999年9月:1998年の排出ガス規制[注 29]に対応するためキャブレターセッティング変更・ブローバイガス還元装置の搭載を実施した1999年モデルに移行。型式名をBA-AA01に変更。
2007年10月:2007年の排出ガス規制[注 30]に対応するため燃料供給装置をインジェクション化した2007年モデルに移行。型式名をJBH-AA01に変更。
2012年5月には小型二輪車日本国外生産移管計画により一旦は生産終了となったが、方針の見直しにより同年9月から熊本製作所での生産を再開。また限定車として2008年にカブシリーズ誕生50周年記念モデルが、2013年に同55周年記念モデルが、2015年に形状立体商標登録記念モデルが発売された。しかし、2016年7月1日に施行された欧州Euro4とWMTCを参考とした規制値および区分の平成28年排出ガス規制をクリアすることが難しいことから、平成24年規制に基く継続生産車である本モデルは2017年8月31日をもって生産終了となった。
2012年モデル[編集]2011年に発表された一部二輪車の生産拠点海外移管計画により、2012年に50cc・110ccのモデルチェンジと中華人民共和国の新大洲本田摩托有限公司へ生産移管を同時にを実施したのが本モデルである。
ベースは2011年にタイで発表された ドリーム110i[注 31] で、以下の日本向けとされた仕様・特徴がある。
車体を50ccモデル・110ccモデルで共用化。
本来の2人乗りシートからシングルシート+リヤキャリアに変更。
尾灯およびテールウインカーのデザインを変更
メーターからギアポジションインジケーターを廃止しスピードスケールを変更。
この結果、型式は50ccモデルがJBH-AA04、110ccモデルがEBJ-JA10となり以下のスケジュールで発表・発売された。
スーパーカブ1102012年2月20日発表、同年3月16日発売。前モデルからは以下の変更を実施。
フレーム剛性の見直し。
ホイールベースを20mm延長。
エンジンを低中回転トルク重視の特性に変更。
車体色はスマートブルーメタリック・パールシルキーホワイト・パールバリュアブルブルー・バージンベージュ・パールプロキオンブラックの5色を設定。
スーパーカブ502012年5月17日発表、同月25日発売。110との差異は多少あるものの基本的には共用する同一車体である。このことから50ccモデルでは54年の歴史で初めて車体構造とエンジンの内径x行程が完全に刷新され、パイプ・ピボットによるバックボーンフレームやテレスコピック式フロントサスペンションの装備、セルフスターター・4段トランスミッションが標準搭載とされたが、車体は上位車種のものであることから車両重量は大幅に増加した。
スーパーカブ50プロ スーパーカブ110プロ2012年7月17日発表、同年9月15日発売。110ccモデルは先代JA07型のフルモデルチェンジ、50ccモデルはプレスカブからの発展的統合の位置づけとされた。
JA07型からは、サスペンションストロークのアップ・メーターケースに作業灯設置・フロントバスケットのフロントマウント化などの改良を実施。車体色はパールバリュアブルブルーのみの設定。
本モデルチェンジにより20,000円強 - 50,000円弱の販売価格引下げも実施されたが、2017年8月31日をもって上述したリトルカブならびに後述するクロスカブと同様の理由で生産終了。
クロスカブ[編集]クロスカブ2012年11月11日に「カフェカブ青山 2012」でCT110(ハンターカブ)の実質的後継としたコンセプトモデルとして初公開されたクロスオーバータイプである。
2013年5月22日発表・同年6月14日発売。2012年モデルをベースにしており、新大洲本田摩托有限公司による生産ならびに型式も共通のEBJ-JA10であるが、車体番号はJA10-400****に区分される。
2017年8月31日をもって上述したリトルカブならびに2012年モデルと同様の理由で生産終了。
派生車種[編集]車名もしくはペットネームにカブを含むモデルは以下の4種類が製造販売された。
スポーツカブ[編集]スポーツカブC110
1960年10月発売。C100のエンジンにハイカムシャフト化・圧縮比9.5・ハイコンプピストン・大型アルミ製シリンダーヘッド装着・サイドドラフトキャブレターならびにロングインテークマニホールド化・オイルラインの変更などのチューンを施工して最高出力4.3→5ps/9,500rpm・最大トルク0.33→0.39kg-m/8,000rpmへアップさせた上で新設計のフレーム・バーハンドル・マニュアルクラッチ・ギア比を見直した3速マニュアルトランスミッション・アップマフラー・大型セミダブルシート・ラバー付き6L燃料タンクを装着するスポーツモデル。1964年にマニュアルトランスミッションを4速へ変更するマイナーチェンジを実施。スポーツカブC110S
1961年8月発売。上述したスポーツカブC110へアップハンドル装着ならびにシングルシート+リヤキャリアを装着したモデル。スポーツカブC115
1961年10月発売。上述したスポーツカブC110へ2人乗車可能とするため54ccエンジンを搭載したモデル。スポーツカブCS90
1964年7月発売。新設計の89ccSOHCエンジンを搭載するスポーツカブC115からの実質的フルモデルチェンジ車。18インチホイール・前輪テレスコピックフォークを装着する。1965年にリヤキャリア・フルチェーンカバーを装着するCS90-2、さらに脱着式ピリオンシートを装備するCS90-3を追加するが、1966年のマイナーチェンジでベンリイCS90へ車名変更。スポーツカブCS65
1964年12月発売。C65同様のSOHCエンジン搭載。上述したCS90とは異なり前輪サスペンションはフルボトムリンク式となる。1966年のマイナーチェンジでベンリイCS65へ車名変更。スポーツカブCS50
1965年発売。上述したCS65の車体に搭載されるSOHCエンジンの内径を44→39mmへ縮小し排気量を49㏄へダウンさせたモデル。最高出力5.2ps/10,250rpm。1967年にベンリイSS50へのフルモデルチェンジを実施し生産終了。ハンターカブ[編集]詳細はホンダ・CT110を参照のこと。
ポートカブ[編集]詳細はホンダ・ポートカブを参照のこと。
カブラ[編集]連結子会社のホンダアクセス[注 32]が製造する純正オプションとなるカスタマイズパーツを装着するモデル。車名はサイドカバーの形状が野菜のカブに似ていることに由来する。
1993年4月20日にフロントマスコット・フロントエンブレム・オリジナルシート・レッグシールド・カブラサイドカバー・ミニキャリア・カブラマーク・専用デザインヘルメットなど全12アイテムを販売店装着オプションとして発売。 1995年の第31回東京モーターショーにCT110をイメージしたハンターカブラを参考出品し、後に市販。1999年の第33回東京モーターショーにはダート仕様にカスタマイズしたダートカブラを参考出品[注 33]。また1998年にはリトルカブ対応用のリトルカブラならびに車両込とするコンプリートモデルを限定車として販売を行うなどバリエーションを拡大した。
2000年代以降は、サードパーティ製パーツも豊富になったこと。ホンダアクセスがオートバイ用純正オプションパーツの製造販売から撤退したこともあり[注 34]、2012年の50㏄・110㏄モデル製造開始に伴い販売終了となった。
現行販売車種[編集]以下のモデルが製造販売される。
2018年モデル[編集]この項目や節には、販売予定の自動車(二輪車・トラック・バス車両・エンジン類を含む)の新型車等に関する記述があります。ウィキペディアは未来を予測する場でも宣伝サイトでもありません。Wikipedia:検証可能性に基づき、正確な記述を心がけ、メーカーが公式発表前の情報については記述を控えてください。また、特に重要と思われることについてはウィキニュースへの投稿も検討してください。2017年10月19日発表、同年11月10日発売。
上述した2012年モデルから平成28年自動車排出ガスに適合させたフルモデルチェンジ車である。モデルバリエーションは2012年モデルから継続で以下の4モデルを設定する。
スーパーカブ50(型式名:2BH-AA09)
スーパーカブ110(型式名:2BJ-JA44)
スーパーカブ50プロ(型式名:2BH-AA07)
スーパーカブ110プロ(型式名:2BJ-JA42)
搭載されるエンジンは2012年モデルからキャリーオーバーのAA04E・JA10E型であるが、2012年モデルからは以下の仕様変更を実施した。
全モデル共通車体デザインを全面変更
生産拠点を熊本製作所へ移管
ヘッドライトをLED化
交換式オイルフィルターを追加
ドレンボルト部にスクリーンフィルターを配置
オイルレベルゲージを挿入ガイド部に設けた形状に変更
シートのウレタン素材と底板形状を最適化
110ccモデルドライブチェーンをサイズアップ
プロのみエンジン停止時でもキーをオンすることで使用可能なポジションランプを搭載
車体色は以下の仕様とした。
スーパーカブ50
パールシャイニングイエロー
バージンベージュ
ムーンストーンシルバーメタリック
タスマニアグリーンメタリック
アーベインデニムブルーメタリック
スーパーカブ110
グリントウェーブブルーメタリック
クラシカルホワイト
バージンベージュ
タスマニアグリーンメタリック
アーベインデニムブルーメタリック
スーパーカブ50プロ/スーパーカブ110プロ
セイシェルナイトブルー
MDシリーズ[編集]MD90(上)スーパーカブ110MD(下)1972年8月に当時の郵政省(現・日本郵政)と共同開発した郵便配達用に特化させたバリエーションである。
MDはメイル デリバリーの略称・型式・バリエーション名であり、本田技研工業社内ではスーパーカブ デリバリー、日本郵便ではMD90 郵政機動車、一般的には郵便カブもしくは郵政カブとも呼ばれる。また車体色は専用の郵政レッドである。
集配および貯金保険業務用営業かばんの装着用にフックが着いたフロントキャリア・積載に対応する大型化リヤキャリやハイマウントタイプのヘッドライトとウインカー・バーハンドル・サスペンションならびにサイドスタンドの強化・狭小路での取り回しを考慮した前後14インチタイヤ・グリップヒーター(一部暖地向けは省略)・寒冷時始動性向上およびアイシング防止用キャブヒーターなどの特化装備が施される。
集配用・貯金保険用の区分も存在する。郵政民営化以後は郵便事業株式会社が集配業務、郵便局が貯金・保険に分割されたが、両者は制服・荷台箱の識別番号・社名ロゴで識別が可能である。
2008年には2011年から後継車両として電動スクーターEV-neoを製造販売する計画を発表。日本郵政も導入を検討していることが報道されたが、法規制や耐久性などの実用面をクリアする必要があり、当面は従来からの郵政仕様車を存続させる方針が採られた。
2016年12月には導入45周年記念のミニチュアモデル付記念切手を発売。
2017年には電動車両による配達に向けて充電ステーションを郵便局に設置するなどの実証実験を行うため日本郵便と本田技研工業が協業することで合意した。
注意点[編集]郵政との共同開発による特化仕様車のため、一般個人・法人への販売はされておらず新車での購入は不可能であるが、用途廃止となった放出中古車の入手は可能[注 35]であり、専門に取り扱う販売店も存在する。
また日本郵便では内規によりそのままの車体色で払い下げることを禁止している[要出典]ことから、廃棄時にはスプレーなどで赤色以外にペイントされる。払下げ後に郵政レッドの車体色へ復元しての登録や公道走行に法的規制は無いが[注 36]、郵便マーク(〒)を除去しない場合は刑法第166条(公記号偽造及び不正使用等)に抵触する。
遍歴[編集]MD採用前の1968年頃にC90Z「郵政省向特別車」が製造納入された。同車はC90一般仕様に以下の変更を実施したものである。
大型特製キャリアをフロント・リアに装備。
ヘッドライトをハンドル上部に移設。
車体色を赤に変更。
その後1971年にC90と輸出仕様のCT90をベースにテレスコピック式フロントサスペンション・アップハンドル・前後輪17インチタイヤ・フロント特製キャリヤ・リヤ大型キャリヤを装備した型式名MD90(K0)を生産開始。
続いて1972年に以下の変更を実施したMD90(K1)に移行した。
アップハンドル装着。
ステアリングステム上部メーター内蔵型ヘッドライト。
前後輪14インチ化。
前後キャリアを大型化。
サイドスタンドを強化。
フロントフェンダー・シートの形状変更。
集配用・貯金保険用の区分。
また、MD90に引き続き原付免許所持者でも乗れるMD50(K0)や70ccエンジンを搭載するMD70(K0)の生産が開始され、MDシリーズは50cc・70cc・90ccのラインナップとなった。以後の大きな変更を以下に示す。
1977年
フロントフェンダー・キャリアの形状変更。標準・寒冷地・沖縄の仕向け地別仕様の設定。1980年
スーパーカブがフレーム内蔵燃料タンクへ変更後も別体タンク旧フレームを継続。スーパーカブ90が85cc新設計エンジンに換装されるもMD90ではCS90をベースとした旧C90系のエンジンを継続。1987年
点火方式をCDI化・電装12V化・MFバッテリーの搭載。1998年
排気ガス規制対策を実施。2004年
MD70の製造終了。2007年
MD50の燃料供給をインジェクション化。2008年
MD90の製造終了。2009年
MD90のモデルチェンジ車としてスーパーカブ110PROをベースにしたスーパーカブ110MDの生産を開始。同車は共通設計のため型式はEBL-JA07となる。2011年
MD50・スーパーカブ110MDの製造終了。2012年
ベース車のスーパーカブモデルチェンジにより、50cc・110ccモデルの共通車体化を実施。郵政向け仕様は、一般向けPROをベースにしたスーパーカブ50MD・スーパーカブ110MDに移行。型式は一般向け同様のAA04型・JA10型であるが、MDシリーズのみ組立は中華人民共和国で行わずに引続き熊本製作所で行われる。排気量クラス 原動機付自転車 メーカー 本田技研工業 車体型式 JBH-AA01 エンジン AA02E型 49cm3 空冷4ストロークSOHC単気筒 -
「中国自動車道」に関する資料情報
中国自動車道の概要 目次へ 
E2A 中国自動車道 アジアハイウェイ1号線路線延長540.1 km(国内2位)制定年1964年(昭和39年)開通年1970年(昭和45年)- 1983年(昭和58年)起点吹田市(吹田JCT)主な経由都市池田市、宝塚市、西宮市、神戸市加東市、津山市、新見市、三次市広島市、山口市終点下関市(下関IC)接続する主な道路(記法)E1 名神高速道路E26 近畿自動車道 阪神高速7号北神戸線E2 山陽自動車道E1A 新名神高速道路E27 舞鶴若狭自動車道E95 播但連絡道路E29 播磨自動車道(予定)E29 鳥取自動車道E73 米子自動車道E73 岡山自動車道E54 松江自動車道E54 尾道自動車道E74 浜田自動車道E74 広島自動車道E9 山陰自動車道(予定)E2A 関門橋■テンプレート(■ノート ■使い方) ■ウィキプロジェクト 道路中国自動車道(ちゅうごくじどうしゃどう、CHUGOKU EXPRESSWAY)は、大阪府吹田市から兵庫県、岡山県、広島県、島根県を経由して山口県下関市へ至る高速道路(高速自動車国道)である。略称は中国道(ちゅうごくどう、CHUGOKU EXPWY)。法定路線名は中国縦貫自動車道であり、当初の道路名はこの法定路線名をそのまま使用していた(道路名を現在の「中国自動車道」に改めた時期は不明)ほか、現在も地図などで「中国縦貫道」などの表記が使用されている場合がある。
なお、吹田JCT - 神戸JCT、山口JCT - 下関ICは アジアハイウェイ1号線にも指定されている。高速道路ナンバリングによる路線番号は、関門橋(関門自動車道)ともにE2Aが割り振られている。路線延長 540.1 km(国内2位) 制定年 1964年(昭和39年) 開通年 1970年(昭和45年)- 1983年(昭和58年) 起点 吹田市(吹田JCT) -
「最高裁判所裁判官国民審査」に関する資料情報
- 「三軒茶屋駅」に関する資料情報
- 「東急田園都市線」に関する資料情報
- 「吉祥寺」に関する資料情報
-
「秋葉原」に関する資料情報
秋葉原の概要 目次へ 
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
独自研究が含まれているおそれがあります。(2008年1月)
あまり重要でない事項が過剰に含まれているおそれがあり、整理が求められています。(2011年12月)
中央通り交差点付近(2007年3月17日)秋葉原の超高層ビル群秋葉原駅電気街口南側の電気街(2004年3月20日)秋葉原駅電気街口北側の電気街(2011年5月28日)万世橋上より電気街を望む(2006年8月)中央通りの歩行者天国(2011年1月23日)秋葉原(あきはばら)は、東京都千代田区の秋葉原駅周辺、主として東京都千代田区外神田・神田佐久間町および台東区秋葉原周辺を指す地域名である。 -
「平成16年台風第21号」に関する資料情報
平成16年台風第21号の概要 目次へ 
平成16年台風第21号(へいせい16ねんたいふうだい21ごう、アジア名:メアリー〔Meari、命名国:朝鮮民主主義人民共和国、意味:やまびこ〕)は、2004年(平成16年)9月に発生し、日本に上陸した台風である。秋雨前線と複合したために豪雨となり、三重県・愛媛県を中心に大きな被害をもたらした。後に、激甚災害に指定された。 発生期間 2004年9月21日 3:00- 2004年9月30日 9:00 寿命 9日6時間 最低気圧 940hPa 最大風速(日気象庁解析) 45m/s(90kt) -
「中国共産党」に関する資料情報
中国共産党の概要 目次へ 
中国共産党(ちゅうごくきょうさんとう、簡体字: 中国共产党、拼音: Zhōngguó gòngchǎndǎng、英語: Communist Party of China, "CPC")は、中華人民共和国の政党。共産主義の実現を最終目標としている。略称は中共(ちゅうきょう)。
2016年末時点で8944.7万の党員を数える。党員数では、2015年にインド人民党(1億1千万党員)に追い抜かれ、世界で2番目に大きい政党である。
中華人民共和国憲法では序言で中国共産党が各民族人民や多党協力と政治協商制度を指導すると規定されているだけでベトナム憲法やキューバ憲法のように共産党が国家を指導するとは直接明記はされていないが、2009年に賈慶林・中央政治局常務委員が人民日報に寄せた『中国の特色ある社会主義路線の上で、中国共産党の指導する多党協力と政治協商制度を不断に整備し、発展させる』によれば、「中国共産党の指導する多党協力と政治協商制度は、西側の二大政党制や多党制のような、一方が政権に就けばもう一方が下野する権力争奪型の政党関係とも、一党制のような権力独占型の政党関係とも異なり、民主的に協議し、互いの心の底まで打ち明けて親しく交わる、斬新な協力型の政党関係なので」あり、「各民主党派と無党派の人々は、中国共産党による指導を自ら進んで受け入れ、中国共産党と親密に協力し、中国の革命・建設・改革事業に共に力を尽くしているのである」と主張されている。中央委員会総書記 習近平 政治局常務委員 習近平、李克強、張徳江、兪正声、劉雲山、王岐山、張高麗 成立年月日 1921年7月23日 全国人民代表大会 2,157 / 2,987 (72%) -
「西室泰三」に関する資料情報
西室泰三の概要 目次へ 西室 泰三(にしむろ たいぞう、1935年(昭和10年)12月19日 - 2017年10月14日[注 1])は、日本の実業家。
株式会社東芝代表取締役社長(後に代表取締役会長を経て、2016年4月時点で相談役)、株式会社東京証券取引所代表取締役会長兼社長、株式会社東京証券取引所グループ取締役会長兼代表執行役、日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長、ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長、第33期慶應義塾評議員会議長、東芝名誉顧問等を歴任。東芝でウェスティングハウス・エレクトリック・カンパニーの買収により巨額損失を出し、その後に社長となった日本郵政の海外事業買収でも同様の巨額損失を出した。その経歴と実績から東芝内部では「東芝の闇将軍」、財界では「肩書コレクター」の異名をとる。生誕 (1935-12-19) 1935年12月19日 日本 山梨県都留市 死没 (2017-10-14) 2017年10月14日(81歳没) 出身校 慶應義塾大学経済学部 職業 実業家 - 「大雪山」に関する資料情報
-
「中国共産党全国代表大会」に関する資料情報
中国共産党全国代表大会の概要 目次へ 中華人民共和国の政治
中国共産党全国代表大会中央委員会中央委員会総書記:習近平
中央政治局中央政治局常務委員会
中央書記処常務書記:劉雲山
中央軍事委員会主席:習近平
中央規律検査委員会書記:王岐山
イデオロギー毛沢東:毛沢東思想
鄧小平:鄧小平理論
江沢民:3つの代表
胡錦濤:科学的発展観
憲法憲法史
1954
1975
1978
1982
法立法システム
中国共産党中央政法委員会書記:孟建柱
司法システム裁判システム
政府全国人民代表大会全国人民代表大会常務委員会委員長:張徳江
国家主席:習近平国家副主席:李源潮
国務院(中央人民政府)国務院総理:李克強(内閣)副総理(常務副総理)
国務委員
国家中央軍事委員会主席:習近平
最高人民法院
最高人民検察院
中国人民解放軍党中央軍事委員会
国家中央軍事委員会中国人民解放軍
中国人民武装警察部隊
統一戦線中国人民政治協商会議全国委員会主席:兪正声
中央統戦部
衛星政党一覧
その他のトピック選挙 (2013)
中華人民共和国の行政区分
中国の人権問題
中華人民共和国の国際関係 (米中関係)
Foreign aid
関連項目: 香港の政治・マカオの政治他国の政治 · 地図政治ポータル表示・ノート・編集・履歴中国共産党全国代表大会(ちゅうごくきょうさんとうぜんこくだいひょうたいかい)は、中国共産党の最高機関。中華人民共和国の政治は中国共産党が指導するため、事実上中国の最高指導機関でもある。略称は中共党大会あるいは党大会。この大会で決められることは、重大問題の討論と決議、党規約の修正、中央委員会、中央紀律検査委員会メンバーの選挙である。 -
「アキュビュー」に関する資料情報
アキュビューの概要 目次へ アキュビュー® (ACUVUE®) とは、ジョンソン・エンド・ジョンソン(Johnson & Johnson)が開発・発売しているコンタクトレンズである。
1日で新しいレンズに交換する使い捨てタイプ (ディスポーザブルタイプ)と最長2週間で交換する頻回交換タイプの2タイプのみを発売している。2016年現在、同社では従来型ソフトコンタクトレンズとハードコンタクトレンズは発売されていない。
全製品がUVカット(UV吸収サングラスの代わりにはならない)であり、2週間交換タイプのレンズケアは煮沸消毒を行わない、マルチパーパスソリューション(MPS)や過酸化水素によるコールド消毒を採用している。また全ての製品は睡眠中はレンズを外す終日装用となっている。
1988年に米国で発売を開始し、日本では1991年から発売を開始した。
日本をはじめ世界65ヶ国で発売されており、2016年現在、コンタクトレンズシェアNo.1を誇っている。
「ACUVUE」という名称の由来は、「ACCURATE(正確な)」と「VIEW(視界)」から作られた造語である。また、「VIEW」の中心には「いつもあなた(U)がいてほしい。」との思いが込められている。 - 「旭岳」に関する資料情報
- 「百里飛行場」に関する資料情報
- 「自由党」に関する資料情報
- 「ZTE」に関する資料情報
- 「CH-53E」に関する資料情報
-
「大津市中2いじめ自殺事件」に関する資料情報
大津市中2いじめ自殺事件の概要 目次へ 大津市中2いじめ自殺事件(おおつしちゅう2いじめじさつじけん)は、2011年10月11日に滋賀県大津市内の中学校の当時2年生の男子生徒がいじめを苦に自殺するに至った事件である。「大津いじめ自殺事件[注釈 1]」「大津いじめ事件[注釈 2]」「大津市○○中学校いじめ自殺事件[注釈 3]」などとも呼ばれる。事件前後の学校と教育委員会の隠蔽体質が発覚、問題視され、大きく報道された。翌年には本事件が誘因となっていじめ防止対策推進法が国会で可決された。 場所 滋賀県大津市 標的 男子中学生(当時) 日付 2011年9月29日、2011年10月8日、2011年10月11日(自殺) 攻撃手段 暴行、器物損壊、窃盗 -
「ラッカ」に関する資料情報
ラッカの概要 目次へ 
ラッカ(アッ・ラッカ、Ar-Raqqah、Rakka、アラビア語: الرقة)は、シリア(シリア・アラブ共和国)北部の都市で、アレッポの160km東にあり、ユーフラテス川中流域の北岸に位置する。ラッカ県の県都。シリア騒乱最中の2013年に『ISIL』(イスラム国)に占領され、2014年の独立宣言以降はラッカを「首都」を宣言し、以降はISILの拠点となった。このため、シリア政府やロシア、アメリカ合衆国、フランス、ドイツ、ヨルダンなどの有志国による空爆作戦が展開され、2017年10月にシリアの反体制派グループシリア民主軍によってようやく陥落した。
ジャズィーラ地方(メソポタミア北部、現在のイラク北西部とシリア北東部にまたがる地域)西部の主要都市で、モースル、デリゾール、ハサカ、カーミシュリーなどと並びジャズィーラを代表する都市のひとつである。人口は190,000人から200,000人と推計されており、シリア第6位の都市。
ラッカはアレッポとデリゾールを結ぶ道路や鉄道が通り、ユーフラテス中流の農産物を集散する農業都市である。ラッカ西方にはユーフラテス川をせき止めたダム湖・アサド湖が広がる。ラッカのすぐ東で北からユーフラテスに合流する支流バリフ川があり二つの川沿いに農地が広がる。バリフ川を北へ遡るとトルコ領に入り、ハッラーンやウルファの平原に至る。国 シリア 県 ラッカ県 郡 アッ=ラッカ郡(英語版) - 計 191,784人 - 「UH-60J」に関する資料情報
カテゴリー
最新記事
(09/07)
(12/16)
(10/14)
(09/06)
(08/21)